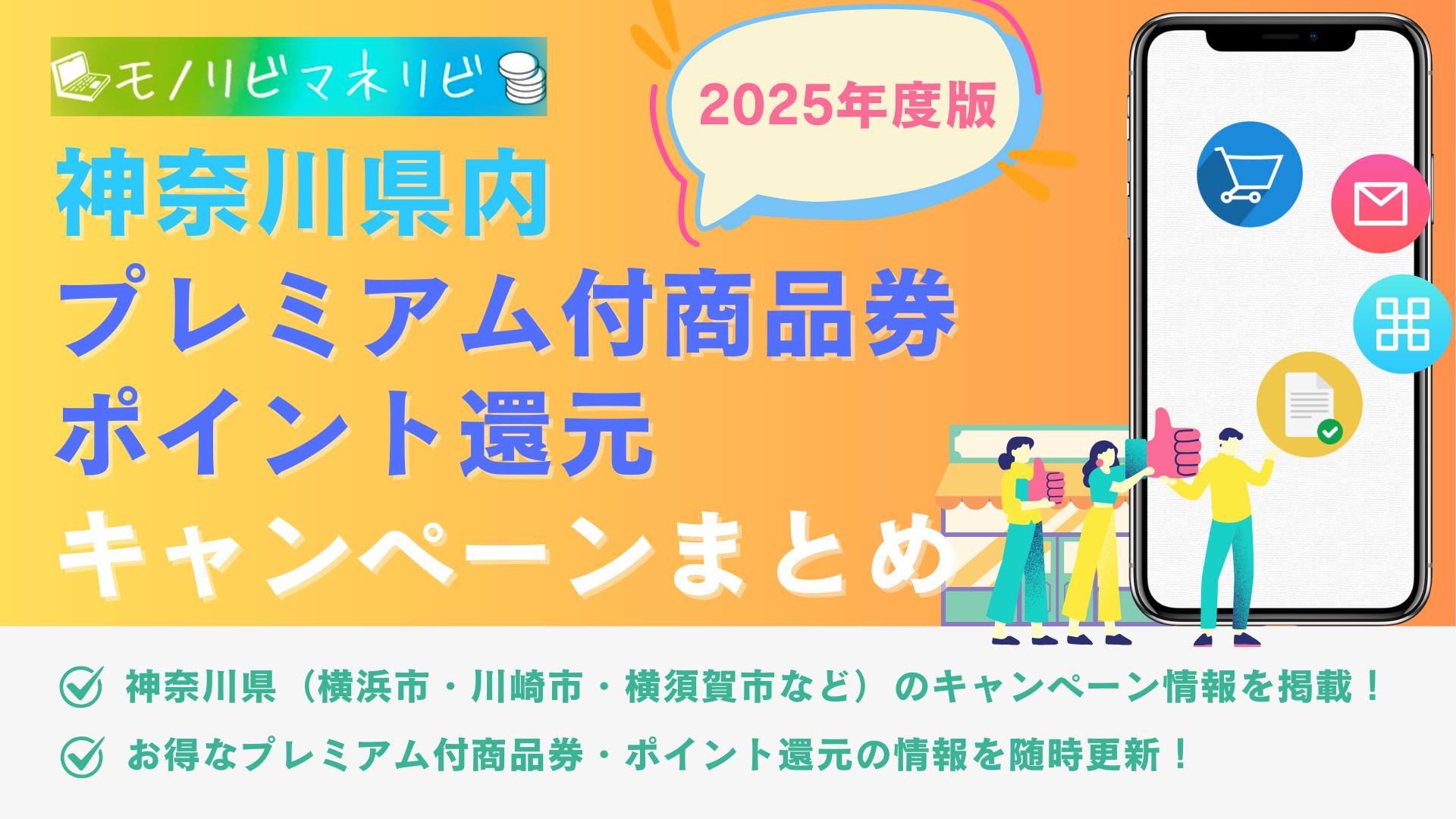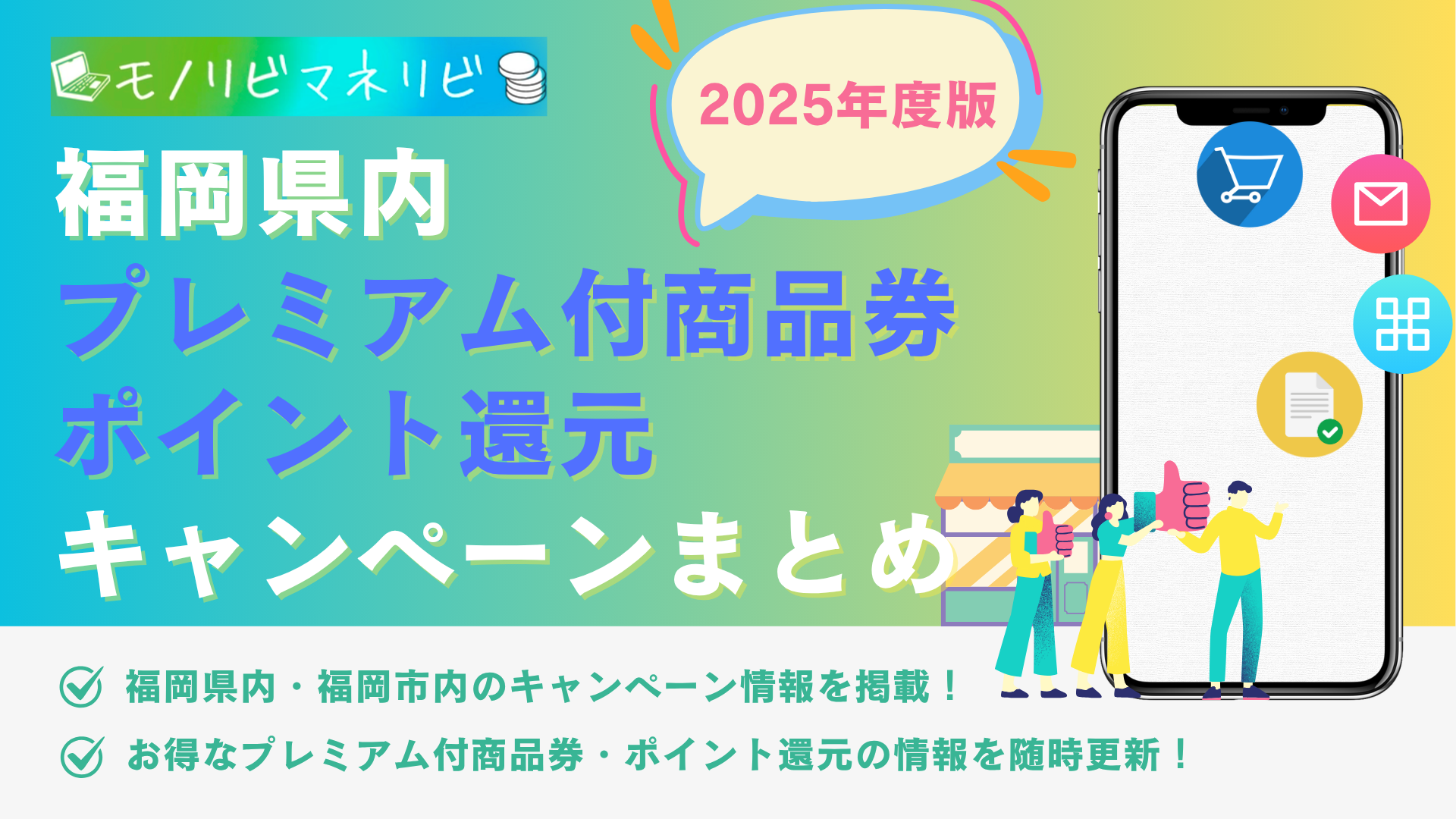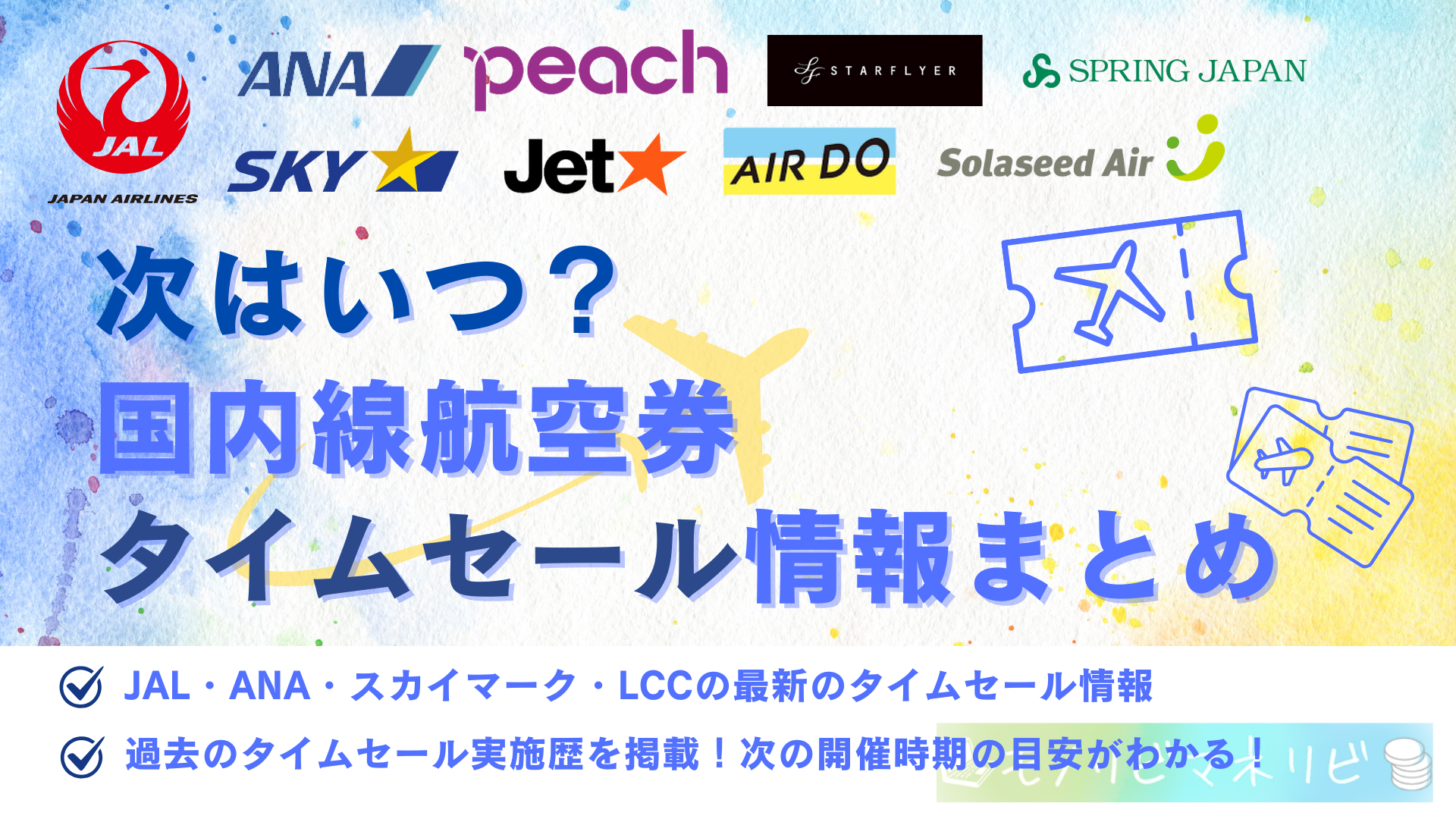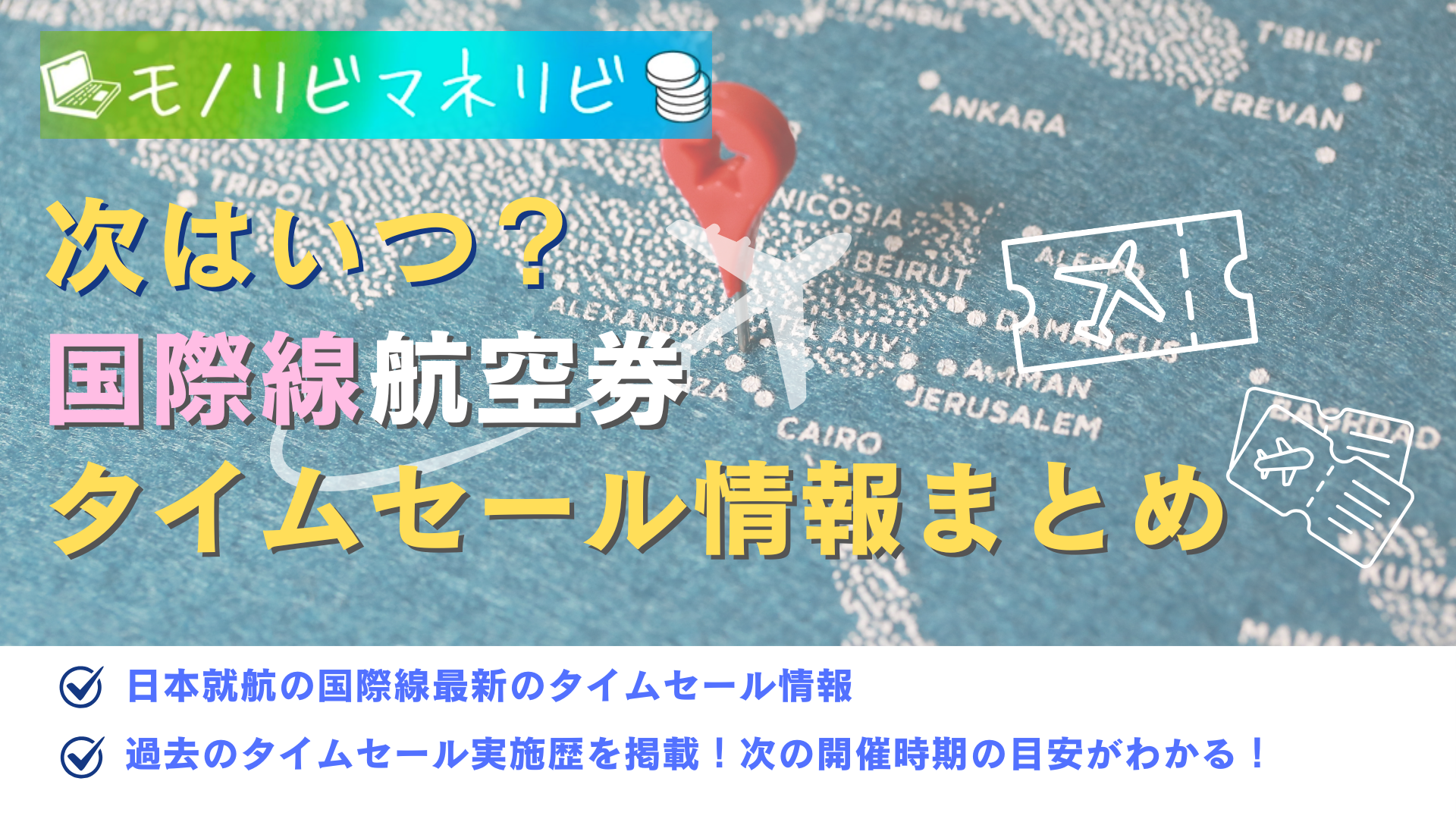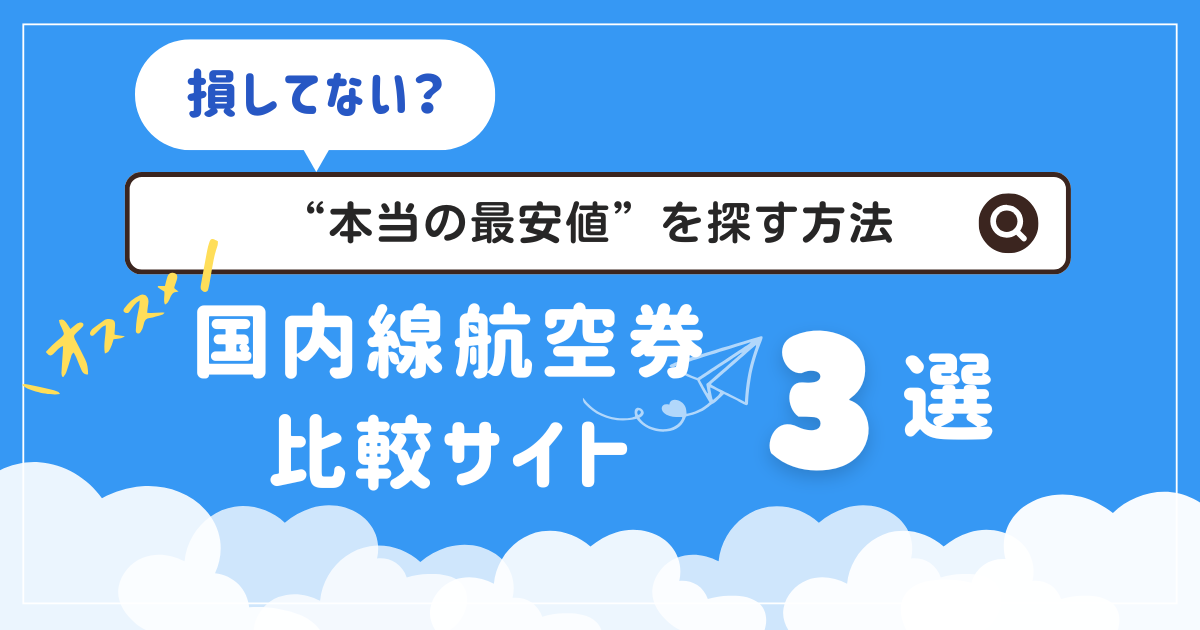本ページでは、全国の自治体で導入されている「デジタル地域通貨」に関する情報をまとめています。
東京においては世田谷区の「せたPay」や渋谷区の「ハチペイ」がデジタル地域通貨にあたります。
お住まいの地域や近隣の自治体でデジタル地域通貨を導入している場合、アプリをインストールしておくことでお得なお買い物ができたり、お得なサービスを受けられることがあります。ぜひチェックしてみましょう!
このページを読むと
- 全国で導入されているデジタル地域通貨について知ることができる!
- デジタル地域通貨の形態が知れる!
- デジタル地域通貨の導入メリットがわかる!
- デジタル地域通貨の課題がわかる!
- デジタル地域通貨の未来がわかる!
東京都23区のキャンペーン情報まとめ
全国のキャンペーン情報まとめ
必ず読んでね
当サイトの内容については、無断転載(コピペ)や商用利用を目的とした画像・記事の使用やそれらの一部の切り抜き、加工などの行為を禁止しております。
当サイトを明記した上での記事の引用(そのままスクリーンショット・キャプチャ等)については、ぜひご自由にご活用ください!
画像(サムネイル画像含む)の転載・切り抜き・加工などの使用は禁止しております。
本記事の内容について
情報については今後変わる可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
なお、本記事によって不利益を被ったとしても当サイトは責任は負いかねますので予めご了承ください。
情報をお寄せください!
当サイトでは、全国で導入されているデジタル地域通貨の情報を集めております。
当サイトに掲載されていない情報をお持ちでしたら、お問い合わせページ(https://monomoney-living.com/contact/)または公式XアカウントのDM(https://twitter.com/monomoneyliving)よりご連絡いただけると幸いです。
目次(都道府県をクリックすると該当箇所に飛べます)
デジタル地域通貨とは?
特定の地域やコミュニティの中だけで使える「電子的なお金(通貨)」です。スマホアプリやICカードを利用し、現金を介さずに決済が行えます。
「地域活性化」や「経済循環促進」を目的に発行され、通常の日本円とは異なり、その地域でしか使えません。
主な特徴
デジタル地域通貨の特徴
- デジタル化・キャッシュレス
・スマホアプリ、ICカード、QRコードなどを使って、現金を使わずに支払いが可能。
・通貨の管理もアプリ上で完結するため、残高確認や履歴管理が簡単。
・ポイントの即時付与や消費もスムーズで、現金のような持ち歩きの不便さがない。 - 地域限定・利用範囲の制限
・使用できるのは特定の市町村や地域内の加盟店のみであることから利用範囲を限定できるため、お金が地域から流出しにくい。
・「地域のためのお金」という性質が強く、他の地域やオンラインでは使えないことが多いため、旅行者や外部からの利便性はやや劣る。 - 独自のプレミアム・ポイント設計
・チャージ額にボーナス(例:10%プレミアム)が付く場合が多い(例:10,000円チャージで11,000分使える)。
・特定の期間・イベント時に「地域独自のポイント還元」も行われる(例:地域イベント参加 → ボーナスポイント付与)。
・ポイントは現金化不可のことが多く、地域内消費を促す仕組みとなっている。 - 行政・地域密着型
・行政サービスと連携し、「災害時の給付金配布」や「子育て支援給付」などにも利用できる。
・通貨そのものが「地域のブランド」としての役割も果たす。
・行政のデジタル施策推進(DX)の一環にもなる。 - コミュニティ形成・体験型価値
・ゴミ拾い、ボランティア、イベント参加などで「地域コイン」が付与されるケースも。
・お金のやりとりだけでなく、人と人の交流も促す設計にすることが可能。 - 環境への配慮・サステナビリティ
・地産地消を促し、地域資源の活用・エコツーリズムと組み合わせる動きも。(例:ローカルフードやエコ活動と連動した地域通貨)
▶︎神奈川県小田原市「おだちん」
▶︎神奈川県鎌倉市「まちのコイン」
▶︎北海道美瑛町「Biei Coin(美瑛コイン)」 - 技術基盤とセキュリティ
・多くはクラウド型の決済システムで運営されている。
・一部の先進地域ではブロックチェーンを活用し、改ざん防止・透明性を担保している。
▶︎岐阜県飛騨高山「さるぼぼコイン」
▶︎福岡県「eumo(ユーモ)」
・個人情報・決済情報のセキュリティ強化は課題。
導入の目的・メリット
デジタル地域通貨の導入メリット
- 地域経済の活性化:お金が地域内にとどまる
・全国チェーンやネット通販ではなく、地元商店やサービスへの支出を促す。
・プレミアム付きやポイント還元で、消費意欲を刺激する。 - 地産地消の促進:地元産品・観光資源の需要拡大
・農産物、加工品、伝統工芸など「地域ならではの商品」に対する消費を後押し。
・観光客向けの「地域体験」や「エコツーリズム」と組み合わせて消費額を増やす。 - コミュニティの形成・地域活動の促進:地域への「愛着」「参加意識」を高める
・ゴミ拾い、ボランティア、防災活動など「お金になりにくい活動」に対し、デジタル通貨で報酬を与える仕組みにできる。
・「体験」や「交流」に価値をつけることができる。
・通貨を媒介に、住民や商店、行政が一体となり、高齢者・子ども・観光客など、多様な人々が交わる。 - エコロジー・サステナビリティ:環境意識を育てつつ、持続可能な地域を支える
・環境配慮型消費の促進(地産地消で輸送エネルギーの削減、プラスチックごみ削減、環境活動の参加報酬にインセンティブを与える)。
・エコツーリズム(自然体験、農業体験、里山整備など)と連動できる。 - 政策手段として活用:迅速・透明・柔軟な行政施策が可能になる
・災害時やコロナ対策時の迅速な支給が可能となる。
・子育て支援や高齢者支援のツールとして活用できる。
・キャッシュレス社会の実現、マイナンバーとの連動の基盤整備となる。 - 行動データ・経済データの活用:「勘」ではなく「データ」に基づく地域運営が可能になる
・消費行動・観光動向の可視化(どのエリアで、どの店舗で、どんな消費が起きているかを把握)できる。
・政策や商業戦略へのフィードバック(補助金・イベントの効果測定に活用)できる。 - 信頼性の向上:利用者・事業者双方が安心して使える通貨基盤になる。
・不正防止・改ざん耐性(ブロックチェーン活用で、取引記録の信頼性の向上)が高まる。
・個人情報の安全管理(分散管理、匿名性の確保)も可能になる。
これらのメリットはデジタル地域通貨の「設計次第」で大きく変わるため、住民や事業者の参加をどう促すか、インセンティブや利便性をいかに高めるように設計するかがカギになります。
課題
デジタル地域通貨の課題
- 高齢者・デジタル弱者への対応
・高齢者やスマートフォンに不慣れな人は利用が難しい。
・デジタルリテラシー格差が広がる可能性。 - 利用動機の不足
・「現金やクレカの方が便利」と感じる人が多く、浸透しにくい。
・金銭的なメリット(割引・ポイント還元)が不十分だと定着しない。 - 利用範囲の狭さ
・加盟店が少ないと使いどころが限定され、「不便」と感じやすい。
・地域外では使えないため「お金の価値」が相対的に低く見える。 - 導入コスト・運用コストの負担
・POSレジの改修や決済端末の導入など初期コストが発生。
・操作方法や返金対応などの習熟も必要。 - 資金繰り・換金性の不安
・地域通貨を現金化するまでのタイムラグや手数料への不安。
・売上が地域通貨で偏り、資金繰りが悪化する可能性。 - 定着と持続性
・最初は話題性があっても、使う人が減ればすぐに廃れる。
・長期的な魅力・必要性を維持するための仕掛けが必要。 - 地域格差の拡大
・人口減少や経済規模が小さい地域ほど、通貨の経済圏が作りにくい。
・都市部と過疎地の間で格差が広がる懸念。 - コストが見合わない
・補助金や予算を投じても、経済効果が目に見えにくいことがある。
・利用率が低い場合、運用コストばかりがかさむ。 - セキュリティとプライバシー
・ブロックチェーンやデジタル技術の安全性確保が不可欠。
・利用者の個人情報や消費行動データの取り扱いに慎重さが求められる。 - 法制度・税制の未整備
・地域通貨に関する法律や税務処理の基準が未成熟。
・会計処理や税申告に混乱を招くことも。 - 通信環境・システム障害
・山間部・離島など通信インフラが弱い地域では使いづらい。
・サーバーダウンやシステム障害時の対応が必須。 - 相互運用性
・他のデジタル通貨やサービスとつながりにくく、利便性が限定される。
・複数の地域通貨が乱立し「分断」が生まれる可能性も。 - サステナビリティとの矛盾
・短期的な経済効果に偏り、真の「持続可能性」が後回しになることも。
課題への解決策
- 人に優しい設計(デジタル弱者も排除しない)
- 持続可能な経済循環(無理のない還元・価値維持)
- 「買う」以外の価値創出(体験・つながり・誇り)
- 段階的な普及と柔軟性(スモールスタート&改善)
デジタル地域通貨の課題解決策
- 高齢者・デジタル弱者への対応
・専用カード型の導入(Suicaのような非接触ICカード)する。
・タブレット決済端末の設置(商店が操作し、高齢者は番号提示のみ)する。
・アナログ手続き(スマホ教室などの支援)を併用する。 - 利用動機の不足
・プレミアム(例:10,000円チャージで11,000円分使える)を付ける。
・地域ならではの体験・サービス交換(「買う」以外の価値を提供)を行う。
・限定特典、抽選による非金銭的価値を創出する。 - 利用範囲の狭さ
・加盟店の拡大支援策(導入費用補助・広報)を実施する。
・複数地域間での共通利用化(インフラ共通化)を図る。▶︎「Payどん」(鹿児島県)
・オンラインショップと連動する。 - 導入コスト・運用コストの負担
・自治体が端末、アプリ導入費を補助する。
・使いやすいUI/UXの提供する。
・商店主向けサポート、研修を実施する。 - 資金繰り・換金性の不安
・即時または週次換金の仕組みにする。
・換金手数料ゼロまたは低額にする。
・資金繰り支援策とのセットで運用する。 - 定着と持続性
・季節ごとのキャンペーンを企画する。
・ガチャ、ポイント、バッジ制度(ゲーム要素)を組み込む。
・地域イベントと連動させる。 - 地域格差の拡大
・複数地域で共同運営(スケールメリット活用)を模索する。
・観光客向けにも開放(住民限定にしない)する。 - コストが見合わない
・段階的に導入し、PDCAサイクルを回す。
・効果測定指標(KPI)を設定する。
・観光消費、防災活用など複数目的で活用する。 - セキュリティとプライバシー
・ブロックチェーンやゼロ知識証明で安全性を強化する。
・第三者機関による監査を実施する。 - 法制度・税制の未整備
・国や自治体でガイドラインを整備する。
・税務サポートを提供する。 - 通信環境・システム障害
・オフライン決済に対応(QRコード/ICカード)させる。
・サーバーを冗長化する。 - 相互運用性
・オープンAPIを採用する。
・マイナンバー、自治体サービスと連携する。 - サステナビリティとの矛盾
・環境活動や社会貢献に報酬を付与する。
・非消費型(学習・交流・健康)への通貨利用を行う。
地域通貨プラットフォーム
地域通貨プラットフォームとは、民間会社などが提供する地域限定のデジタル通貨(地域通貨)の発行・流通・決済・管理を支えるIT基盤です。最近はスマホアプリやQRコード決済が主流で、ポイントシステムやクーポンと一体化して提供されることが多くなっています。
- Pokepay(ポケペイ):ふくアプリ、さのぽ
- chiica(チーカ):ネギー、カナちゃんコイン、Meji-Ca
- MONEY EASY(マネーイージー):させぼeコイン、ゆでぴ、さるぼぼコイン
- Payどん(ペイドン):鹿児島県内のプレミアム付商品券共通プラットフォーム
- yuifill(ユイフィル):ゆうすいポイント、かこがわウェルピーポイント
既存の地域通貨プラットフォームを利用するメリット
- 短期間・低コストで導入可能
・既存の汎用プラットフォーム(chiica、Payどん、など)を使えば、一からシステムを開発する必要がなく、早期スタートが可能。
・カスタマイズも柔軟で、規模やニーズに応じたプランが選べる。
・子育て支援、健康ポイント、福祉支援、観光振興など複数の事業に対応可能。 - 住民・利用者のメリット
・スマホアプリ1つで地域の買い物・イベント・行政サービスが利用できる。
・プリペイドカード型と併用できるプラットフォームもあり、デジタル慣れしていない層でも安心。
デジタル地域通貨の具体的事例
- 技術解決・アナログ活用(ICカード・QRコード簡素化・代行支援)
- 店舗への支援(無料導入・負担軽減・簡単操作)
- 利用者への支援(デジタル教育・アナログ併用・参加型イベント)
- 観光客への支援(地域外利用・リピーター優遇・ネット活用)
- 財源(広告・企業協賛・補助金)
岐阜県飛騨高山地域「さるぼぼコイン」
主な課題
- 高齢者や観光客にアプリ操作が難しい。
- 商店主のデジタル機器への不慣れ。
- 利用者のリピート率が伸び悩み。
主な解決策
| 課題 | 解決策 |
|---|
| 高齢者・IT弱者の排除 | カード型「さるぼぼカード」導入し、商店に設置するタブレットでスタッフが代行入力する |
| 加盟店対応の負担 | 簡易型決済ツールの提供(QRコード印刷のみでもOK) |
| 観光客利用促進 | 観光地・宿泊施設での特典・割引との連動→ 旅行終了後もネットショップで使える |
大阪府泉佐野市「さのぽ」
主な課題
- 市民・事業者の認知度不足。
- キャンペーン終了後の利用減少。
- システム利用料への不満。
主な解決策
| 課題 | 解決策 |
|---|
| 認知度向上 | 小中学校・高齢者施設への周知・連動
地元メディア・FMでの継続した宣伝を行う |
| 持続利用 | 健康ポイント・ボランティアポイントとの統合で「お金以外の価値」でも貯まる仕組み |
| コスト負担 | 広告料収入を財源化し、自治体補助による負担軽減を図る |
鹿児島県奄美市「Yui Coin」
主な課題
- 利用者数が少なく経済効果が限定的。
- 観光客の一過性利用のみ。
主な解決策
| 課題 | 解決策 |
|---|
| 地域住民の利用促進 | 島民限定で還元率アップ
コミュニティイベントでのYui Coin活用を必須化 |
| 継続的観光客利用 | 「来島履歴」を活用しリピーター優遇
他の地域やオンラインでの利用提携を図る |
北海道下川町「Machi Pay」
主な課題
- 使える店が少なく利便性不足。
- デジタルリテラシー格差。
主な解決策
| 課題 | 解決策 |
|---|
| 加盟店の拡大 | 初期導入コスト0円
オペレーション代行サービス |
| 高齢者対応 | 紙クーポンとの併用を開始
移動型「デジタル教室」の実施 |
デジタル地域通貨の未来
デジタル地域通貨の未来
- 地域経済の「再構築」と「自立化」:新しい消費圏の形成。物だけでなく体験・サービス・文化消費への転換。
・地域通貨が地元の経済圏を強化する。
・消費の地域内循環率の向上 → 地元商店・農業・観光の活性化。 - 地域共生社会・つながりの再生:通貨がコミュニティの絆を生む社会。「稼ぐ・使う」だけでなく「支え合う・楽しむ・育てる」経済。
・デジタル地域通貨がボランティア・健康づくり・子育て支援など「貨幣に換算されなかった価値」を生み出す。
・高齢者、子ども、障がい者も含めた「誰一人取り残さない経済」の実現。 - 次世代技術との融合:スマホレス社会(ウェアラブル・生体認証)でもスムーズな決済を実現。
・地域コイン+NFT:地域の特産品・伝統工芸・観光体験をデジタル資産化。
・ブロックチェーン:安全・透明・改ざん不可の取引履歴。
・Web3・DAO:地域住民が自治・運営に参加する「民主的通貨」。
・AI×IoT×通貨:行動に応じたリアルタイムインセンティブ、健康・防災・交通管理とも連動。 - 環境・SDGsと通貨の融合:環境活動・防災・健康促進が「経済行動」と連動する。
・地元産品、再生可能エネルギー、リサイクル活動に対し、インセンティブを与える設計が重要に。
・CO₂排出削減、循環型社会の支援ツールとして機能。 - 自治体運営のデジタル化:マイナンバー・地域通貨・地域ポイントが一体化。地方自治体が政策効果を可視化・迅速化できる社会。
・地域通貨が公共サービス・税金・給付金と統合。
・行政DX(デジタルトランスフォーメーション)の鍵に。 - お金の「意味」が変わる:貨幣=地域への愛着と参加のシンボルに。使うほどに「人」と「まち」が豊かになる。
・「どこで・誰と・何のために使うか」が重視される。
・利便性よりも「共感消費」「地域貢献消費」が価値を持つ。
デジタル地域通貨は、地域経済を活性化し、キャッシュレス社会を進める鍵となる可能性を秘めていますが、普及には「使いやすさ」と「地域全体の連携」が重要です。
デジタル地域通貨は、通貨としての役割にとどまらず、「経済」「社会」「環境」「行政」の課題を統合的に解決する目的として導入されます。つまり、社会貢献・環境行動・健康行動・文化継承も価値化させることができ、地元商店だけでなく、教育・福祉・医療・観光・防災とも連動させることができます。
そのため、行政・民間・住民・観光客が共に使い、共に育てる仕組みづくりが重要であり、単なる「買い物促進」にとどまらず、地域の未来づくりのツールとして位置づけることが大切です。
全国のデジタル地域通貨 一覧
全国の各自治体において、さまざまなデジタル地域通貨が導入されています。このページでは導入されている地域通貨をまとめています。
デジタル地域通貨では、さまざまなプレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンが実施されています。
これらのキャンペーンは、地域や実施時期によって内容が異なります。プレミアム付商品券の場合、購入対象者が在住者に限定されることが多いですが、ポイント還元キャンペーンは誰でも参加できるケースが多いです。
各自治体のキャンペーン情報は随時更新されますので、最新情報をこまめにチェックすることをおすすめします。特に人気の高いプレミアム付商品券は、申込期間や販売数に制限がある場合が多いため、早めの確認が重要です。
なお、キャンペーンの利用にあたっては、使用可能な店舗や期間、還元上限額などの条件をよく確認しましょう。プレミアム付商品券やポイント還元を上手に活用することで、日常の買い物をよりお得に楽しむことができます。
表の見方
実施中のキャンペーンとして掲載しているものは以下のとおりです。
- 形態:利用できる媒体を掲載。「アプリ型(デジタル)」or「カード型(アナログ)」、もしくは両方から選べる形にしているかはデジタル地域通貨の設計による。
- 行政連携:行政サービスと関連があるか(予定も含む)。
・行政(イベント・災害・地域)などの情報提供
・自治体などが実施しているイベント参加やボランティア活動への参加、清掃活動への参加、健康づくりイベントへの参加などでインセンティブ(ポイント還元など)が受けられるか
・子育て支援などの給付金や物価高騰対策の給付金など、自治体からの給付をデジタル地域通貨で受け取れるか
・デジタル地域通貨で税金などの納付ができるか - 【通年】還元(pt還元・チャージ還元):年間を通して、ポイント還元やチャージによる還元を受けられるかどうか。(pt還元:支払額に応じてポイントが付与される仕組み。チャージ還元:地域通貨へのチャージ額に応じてポイントが付与される仕組み)
- キャンペーン(プレミアム・ポイント還元・チャージ還元):不定期にデジタル地域通貨でプレミアム付商品券の発行やポイント還元キャンペーン、チャージによるポイント還元キャンペーンなどが実施されたことがあるかどうか。
デジタルのプレミアム付商品券専用に構築された「⚪︎⚪︎Pay」「⚪︎⚪︎ペイ」については、掲載から除外しています。
通年でポイント還元等を実施している、行政イベントとの連携、給付金の受給ができるかの機能を有しているものを主に掲載しています。
北海道
東北地方
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
関東地方
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
中部地方
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
近畿地方
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
中国・四国地方
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
九州地方・沖縄
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
東京都23区のキャンペーン情報まとめ
全国のキャンペーン情報まとめ